皆さんこんにちは。今回は「災害時のSNS情報との向き合い方」について解説していきます。
いまや誰もがスマートフォンを持ち、SNS(X、Instagram、LINEなど)を通じて情報を発信・取得する時代ですよね。
特に災害時は、テレビやラジオよりも先にSNSで情報を得ることも多くなっています。
しかし便利な反面、SNSには誤情報やデマも多数流れるという落とし穴があります。では、どのようにして正しい情報を選び、デマに振り回されないようにするか?一緒に考えていきましょう。
1. デマが生まれる背景とは?
まず、なぜ災害時にデマが多くなるのでしょうか?
- 「善意の拡散」が逆効果に:誰かの役に立ちたい、助け合いたいという気持ちから、未確認情報を拡散してしまうことがあります。
- 不安心理が拡大を助長:不安な時は人は「悪い情報ほど信じやすい」傾向にあり、結果として誤情報が一気に広がります。
- 過去の災害のコピペ情報:例えば「○○の動物園からライオンが逃げた」「有名人が寄付した」という過去のデマが、再びコピーされ拡散されるケースも。
こうした情報に踊らされると、避難の判断を誤ったり、被害を拡大させたりする恐れがあります。
2. 情報の信頼性を見極めるポイント
では、信頼できる情報と、そうでない情報はどう見分ければよいでしょうか?
- 「発信元」が明確かどうか:政府機関(内閣府、防災科研、自治体)や、気象庁、消防・警察などの公式アカウントを優先的にチェック。
- 一次情報かどうかを確認:「誰かが言ってた」ではなく、「自分で見た」「公式が発表した」など、情報源をたどれる内容かを判断。
- 拡散希望の文言に注意:「拡散希望」「至急!」など、強い言葉で感情を煽る投稿は要注意。
- スクリーンショットは要確認:偽装された画像も多く存在するため、投稿日時やアカウント名をよく確認しましょう。
3. 正しい情報の集め方とツール活用
信頼できる情報を素早く入手するために、以下の方法が有効です。
- X(旧Twitter)のリスト機能を活用:防災アカウントだけをまとめておけば、不要な情報に振り回されにくくなります。
- 防災アプリを併用:「Yahoo!防災速報」「NHKニュース・防災」などは速報性・信頼性が高い。
- 自治体の公式LINE登録:多くの市区町村が公式LINEで避難情報やライフライン状況を配信しています。
- リアルタイム検索は慎重に使う:「地名+火事」「○○川 決壊」などで検索すると状況は掴めますが、裏取りが必要。
4. 自分が拡散する側になるときの注意点
あなたが「情報を発信・拡散する側」になるときは、次のことを意識しましょう。
- 必ず出典を明記する:「○○市公式」「NHKより」など、情報元が確認できる形で発信。
- 個人情報の扱いに注意:避難所の状況や写真を投稿する際、顔や名前などが写り込まないよう配慮。
- 共有する前に一呼吸:本当に必要な情報か?誰かの役に立つか?冷静に考える習慣を。
- 誤情報に気づいたら訂正を:拡散してしまった後でも、間違いと気づいたら削除・訂正して謝ることが大切です。意外とできないところかも知れませんね。
まとめ:SNSは「使い方次第」で武器にも凶器にもなる
いかがでしたか。
災害時のSNSは、正しい使い方をすれば「命を救う情報源」にもなりますが、使い方を間違えれば「命を危険にさらす凶器」にもなり得ます。
✔️ 発信元を必ず確認し、信頼できる情報だけをチェック
✔️ アプリやリスト機能を活用して、情報の整理・信頼性を高める
✔️ 「自分が発信するとき」は出典と正確さを重視
✔️ 疑わしい情報は「拡散しない勇気」も大切
災害時は混乱がつきものだからこそ、冷静な情報リテラシーが命を守る鍵になります。今のうちに準備しておきましょう。
今回もありがとうございました。


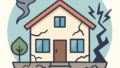

コメント