皆さんこんにちは。今回は、土砂災害に備えるためのハザードマップ活用術について解説していきます。
もうすぐ、梅雨や台風の時期ですね。豪雨による土砂災害は突然私たちを襲ってきます。
特に、山間部や斜面近くに住んでいる場合、リスクは大きくなりますよね。
そんな時、あらかじめ「ハザードマップ」を活用することで、被害を軽減するための備えができます。
しっかり活用できるよう、見るべきポイントと見方を確認しておきましょう。
1. ハザードマップとは?基礎知識を押さえよう
ハザードマップとは、自然災害が発生した際に被害が想定される範囲を示した地図です。
市区町村が作成し、役所やホームページで無料配布されています。
土砂災害に関するハザードマップには、
- 土砂災害警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 浸水想定区域(豪雨時に併せて表示されることも)
などが色分けされ、リスクの程度が一目でわかるようになっています。
自分の家や職場、学校がどの位置にあるか、事前に確認しておくことが大切です。
2. 土砂災害警戒区域とは?リスクを正しく知る
ハザードマップを見ると、「黄色」や「赤色」で示された区域が目につきます。
これは次のように分類されています。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
→ 土砂災害による被害のおそれがあり、警戒が必要なエリア。 - 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
→ 命に危険が及ぶ可能性が高く、建築物の構造規制がかかる厳重注意エリア。
自宅や職場がこれらの区域に該当している場合は、特に早めの避難行動が必要です。
また、道路が土砂で寸断される可能性もあるため、避難経路も複数パターン考えておきましょう。
3. ハザードマップを使った避難計画の立て方
ハザードマップを活用した避難計画は、以下のステップで立てるのが効果的と考えられます。
- 自宅・職場・学校などの位置をマップ上で確認する。
- 土砂災害のリスク(警戒区域・特別警戒区域)を把握する。
- 安全な避難所を複数チェックする。(できれば徒歩で行ける範囲)
- 避難ルートを確認し、家族と共有する。
- 夜間や雨天時でも避難できるよう、懐中電灯やレインウェアを備える。
特に子どもや高齢者がいる家庭では、移動に時間がかかることを想定し、早めの避難を心がけましょう。
4. ハザードマップは定期的に確認・更新しよう
ハザードマップは一度見ただけでは不十分です。
都市開発や自然環境の変化により、区域が見直されることもあります。
最低でも年に一度、防災週間(9月)や防災の日(3月)などのタイミングで最新のハザードマップをチェックしましょう。
また、スマートフォンアプリや防災ポータルサイトを利用すると、リアルタイムの気象警報と連動してリスクを確認できるので便利です!
防災ポータルに関する記事はこちら「自治体の防災サービスを活用しよう」
まとめ
いかがでしたか。
土砂災害は一瞬にして生活を奪う災害です。
しかし、事前の情報収集と準備次第で命を守ることは十分可能です。
✔️ 自宅・職場・学校がハザードマップ上でどこにあるか把握する
✔️ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域を確認
✔️ 複数の避難所と避難ルートを確保する
✔️ 家族間で避難計画を共有
✔️ 定期的にハザードマップをチェック
ハザードマップを「見るだけ」ではなく、「使いこなす」ことで、いざというときに冷静に行動できるように準備していきましょう。
今回もありがとうございました。



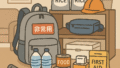
コメント